
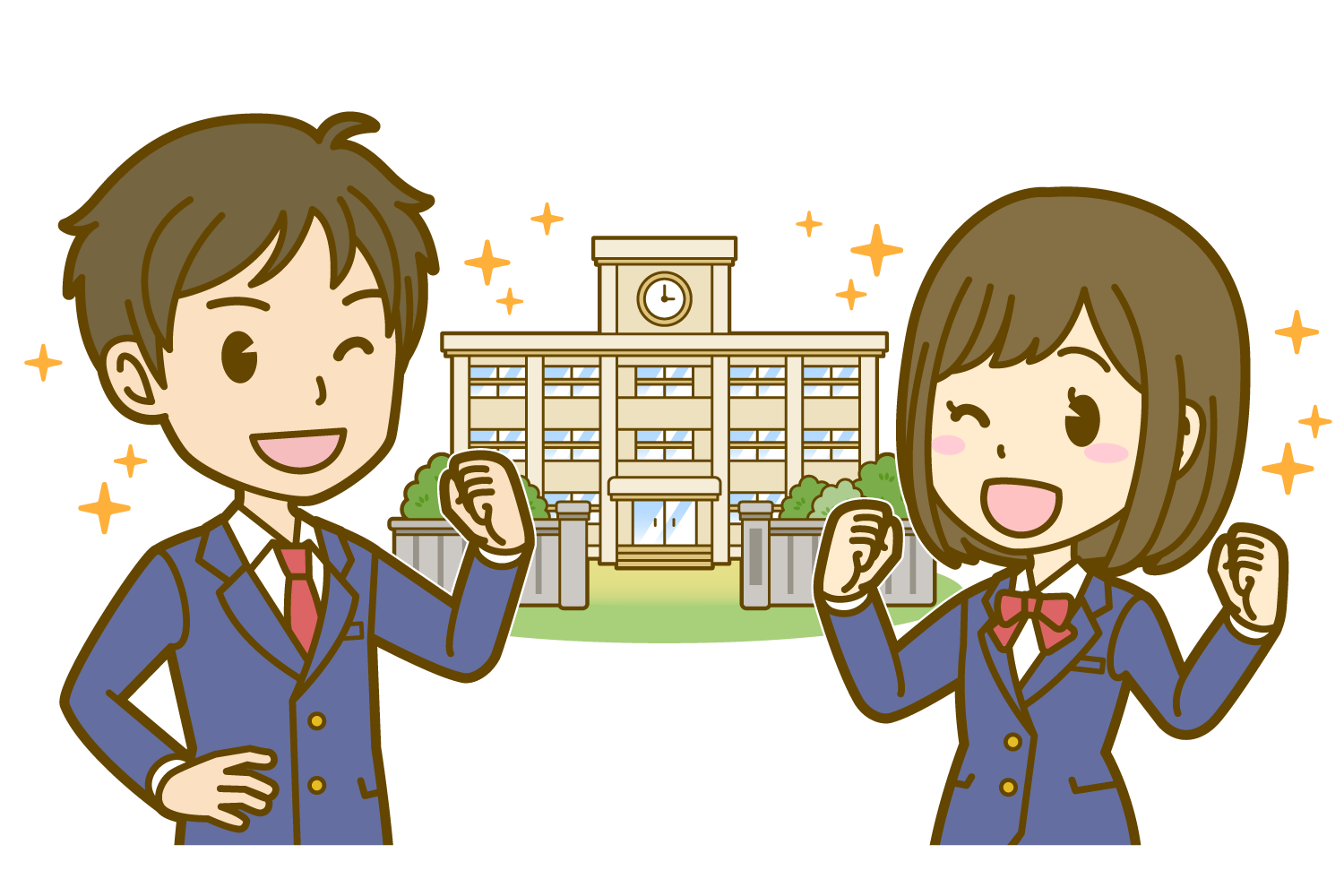
受験に向けて必死に勉強しているけれど、中々思ったように点数が伸びていかない、という気持ちを持っている方は少なくないと思います。
そのような方に一度試してみていただきたいのが、今までの模擬テストや実力テストの結果をしっかり振り返ることです。点数だけでは何が足りないのか、どういう対策を取ればよいのかを確実に判断することは難しいです。
御嵩町の教育支援センター情報を追加しました。
可児市の教育支援センター情報を追加しました。
小学校・中学校の不登校の状態にある児童生徒に向けて、学校復帰や社会自立できるよう支援する様々な機関・施設が存在します。 教育支援センター 県及び市町村教育委員会等が設置する施設に、教育支援センター(適応指導教室)がありま…
瑞穂市、本巣市の教育支援センター情報を追加しました。
瑞穂市、本巣市の教育支援センター情報を追加しました。
山県市の教育支援センター情報を追加しました。
岐阜市、各務原市、羽島市の教育支援センター情報を追加しました。
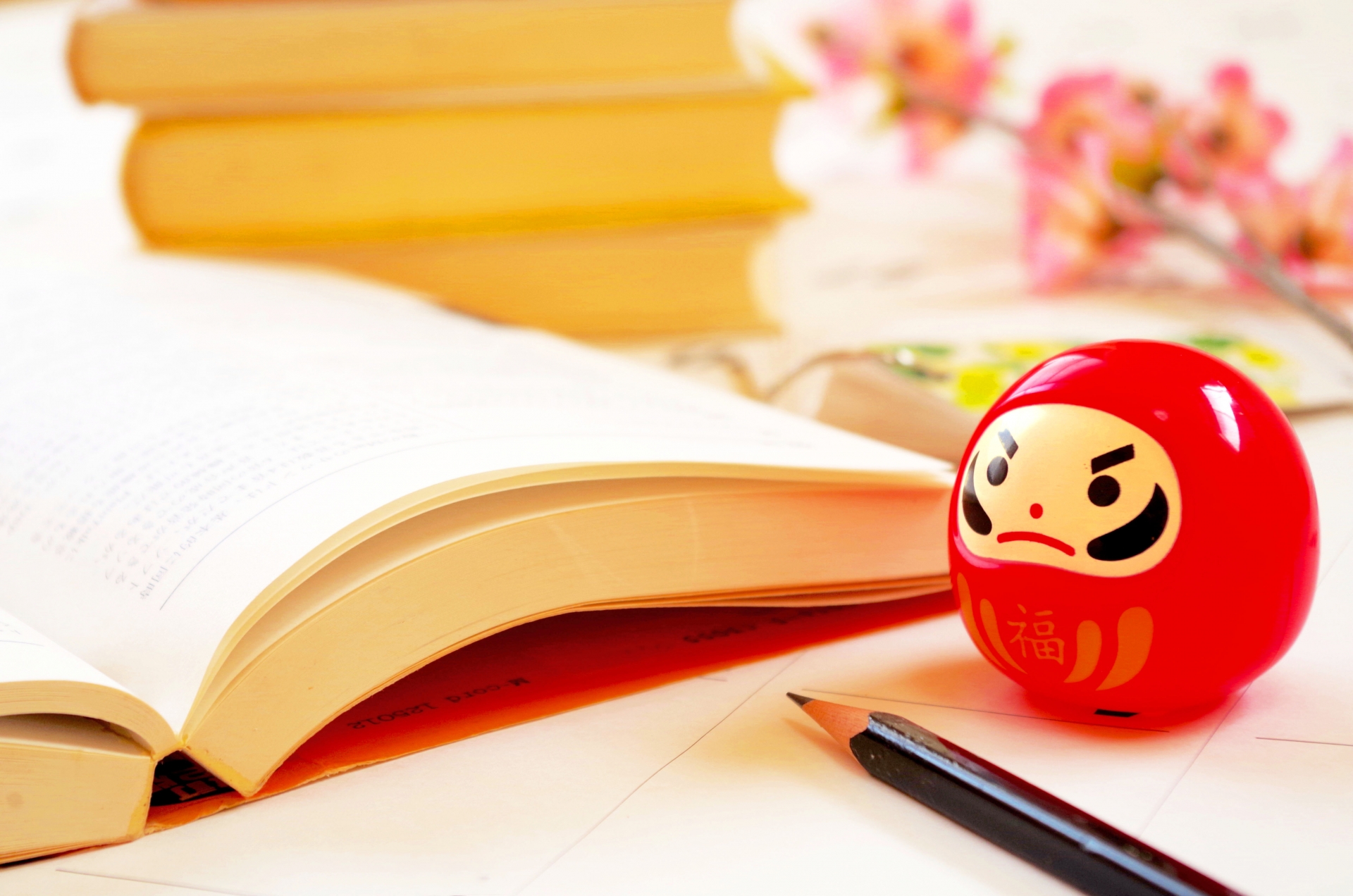
受験に向けて勉強しよう!と考える時に、どのように勉強すれば良いか多くの人が迷う教科が国語ではないでしょうか?数ある教科の中では、覚える必要がある単語などは少ないですが、それ以外の技能に依存している部分が多いため、どう手を着けていけば良いか分からなくなる事が多い教科です。
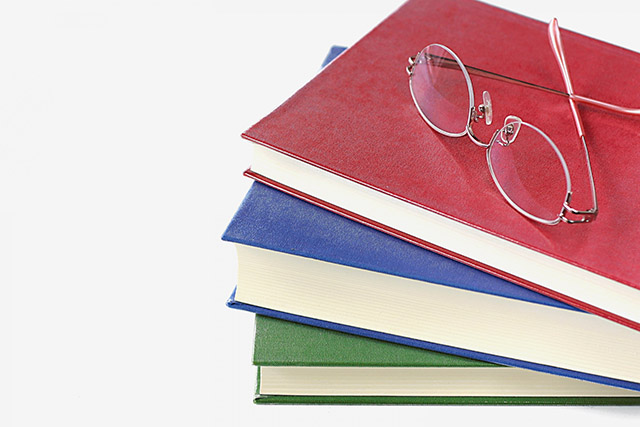
社会科目は様々な分野に分かれており、それぞれ特徴もありますが、共通する大きな点として、暗記が大部分を占めている科目である事が言えます。暗記が必要になる頻度が他の教科に比べてかなり多いため、暗記が得意かどうかが顕著に出てしまう科目です。しかし、暗記以外に必要となる部分も存在します。
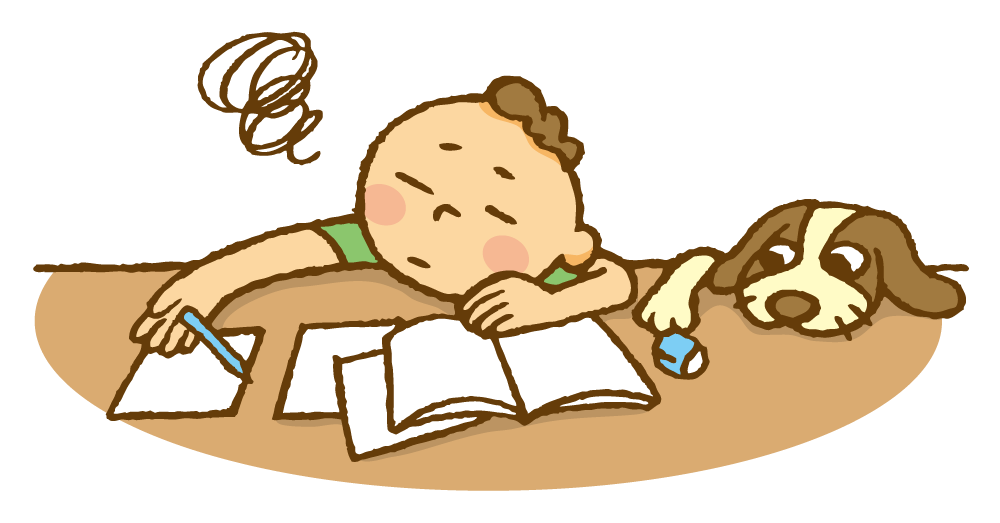
理科の大きな特徴として、それぞれの単元によって勉強していく内容に大きな差があり、広い分野の知識が必要になってくることです。生物、物理、化学、地学、気象など、それぞれの単元が別々の特色を持っています
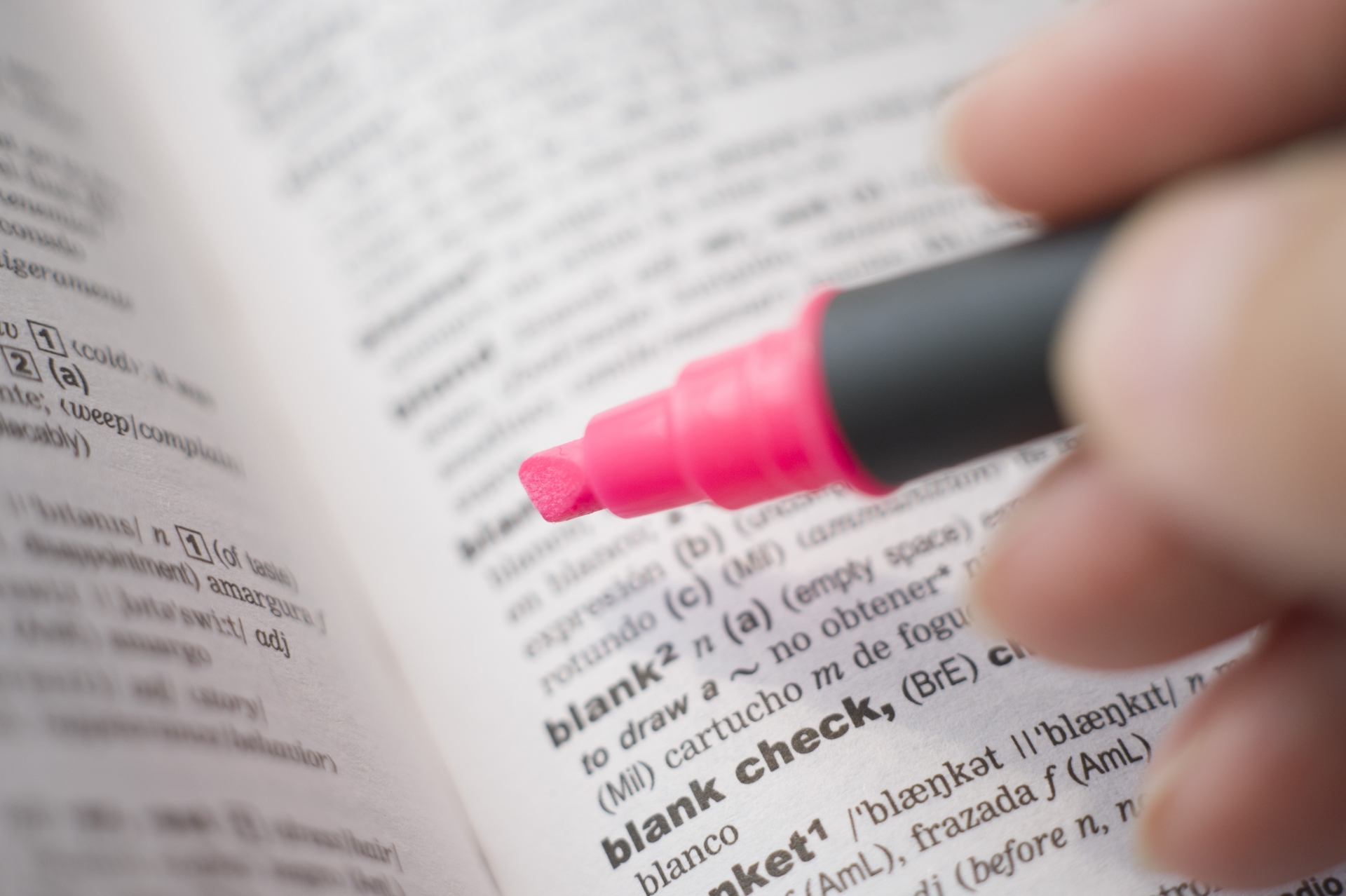
英語の大きな特徴は、既習範囲の知識がかなり必要になってくることです。数学などでも以前の範囲で培った知識が必要なことはありますが、英語はほぼ全ての範囲の知識が必要になってきます。英語の成績を上げたいときは、まずは英語の継続的な勉強習慣を身につける事を目標にしましょう。

勉強における苦手科目は何か、という質問に対して、多くの生徒が数学が苦手であると答えます。多くの方が苦手意識を持ってしまっている数学ですが、受験に向けて勉強を進めて行く場合はどういったことに注意していくのがよいのでしょうか?
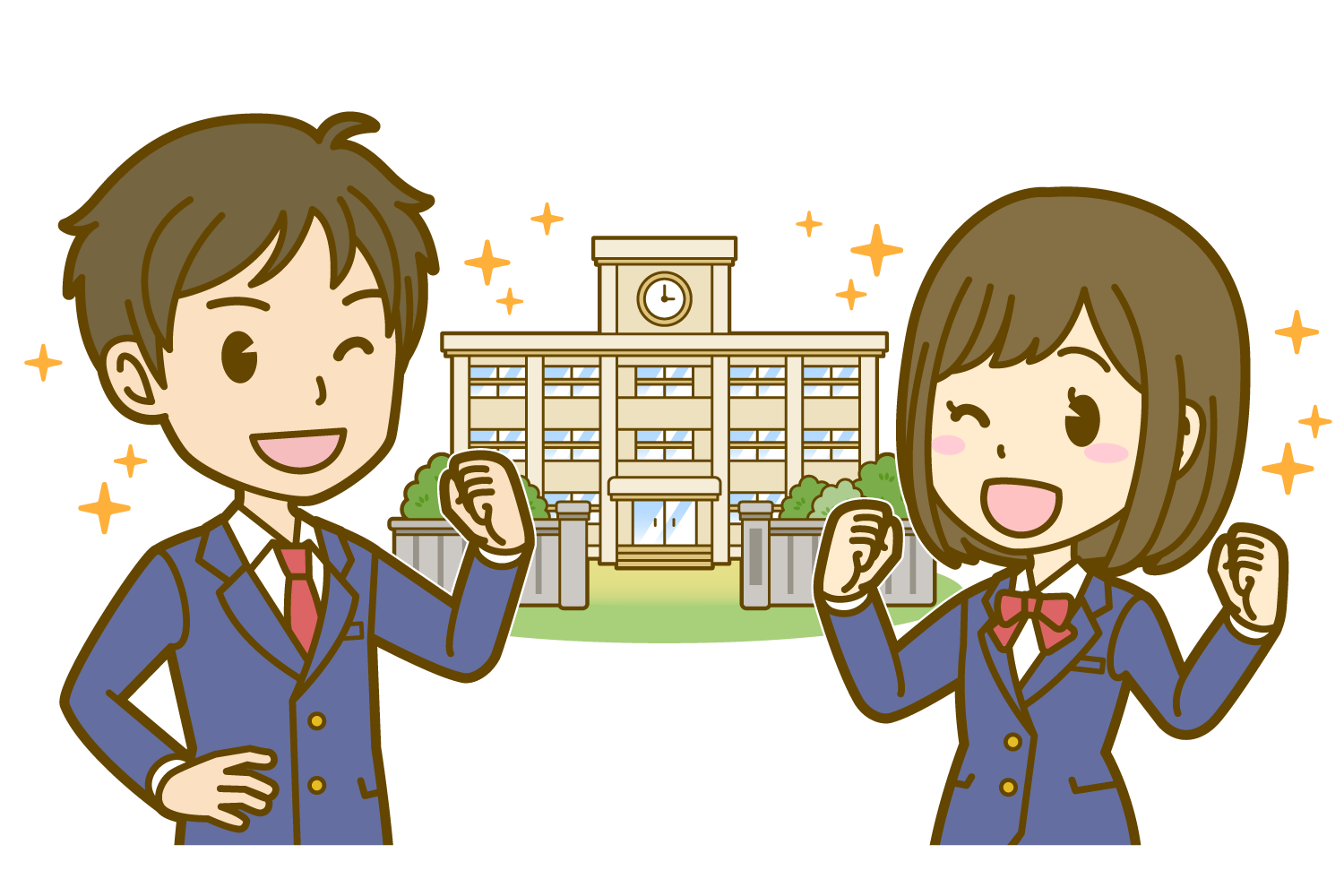
現状を整理した後にするべき事としてオススメしたいのが、受験を目指す上で達成すべき目標の設定です。その時に大事にして頂きたいのが「現実的」で「具体的」で「効果的」な目標の設定の仕方を知っておくことです。それはどういうことなのか?それぞれについてさらに深く見ていきましょう。

起立性調節障害とは、自律神経系の異常等で循環器系の調節がうまくいかなくなる疾患です。好発年齢は10~16歳、有病率は、小学生の約5%、中学生の約10%とされ、女性の方が1,5~2倍起こりやすいとされています。起立性調節障害は軽症であれば症状を緩和するための注意をしていくだけで症状をコントロールできます。以下の改善策の中で、できることから取り組みましょう。